
- 引っ越し前にやること
- 住所変更
引っ越しで印鑑登録の住所変更手続きは必要?
更新日:2023年9月14日

対応が義務付けられているものではありませんが、印鑑登録の手続きについても確認しておきましょう。引っ越し後に印鑑証明書が必要になることもあり、印鑑登録が完了していなければ印鑑証明書を発行することはできません。引っ越し時に済ませておけば後から慌てて手続きをしなくてよく、効率的です。印鑑登録の手続きについて役立つ情報を紹介していきます。
印鑑登録とは
印鑑登録とは、市区町村役場へ印鑑を正式に登録することによって「自分だけの印鑑」であることを証明するために行う届出です。
印鑑登録ができるのは15歳以上(被後見人は除く)で、1人につき1個の印鑑を登録することができます。
また、印鑑登録を行った証明として「印鑑登録証」(カード)が発行されます。
印鑑登録された印鑑を「実印」と呼び、法律上、社会上の権利や義務の発生を伴う非常に重要なものですので、安全な場所で保管しておきましょう。
実印が必要な場面としては公正証書や借用書、契約書の作成のほか、不動産取引、自動車購入、保険金受領などが挙げられます。
印鑑証明書とは
印鑑登録をするきっかけとして、印鑑証明書が必要な場面が少なくありません。「印鑑証明書」は印鑑登録を行った際に発行される「印鑑登録証(カード)」とは別の物で、押印した実印が本人のものであることを証明する大事な書類です。実印と印鑑証明書によって本人が実印で捺印した書類であることが認められるため、本人になりすました第三者が契約してしまうことを避けられます。
印鑑証明書には実印の印影だけでなく住所、氏名、性別、生年月日などが記載されています。
印鑑証明書は自治体の窓口や出張所、市民センターなどの窓口で申請書を提出することで交付されますが、先に印鑑登録を済ませておく必要があります。1通あたり200〜300円程度の手数料と、印鑑登録証(カード)の提出を求められますので忘れないようにしましょう。
コンビニでも印鑑登録証明書の交付を受けることができます。ただし、手続きには利用者証明用電子証明書が登録されたマイナンバーカードが必要です。窓口での発行より手数料が減額されている自治体もあります。交付可能な時間が決まっていて24時間対応ではありませんが、早朝や夜間、休日など窓口が開いていない時でも手続きができ、その場で発行されます。窓口の営業時間内に行くことが難しい場合や、窓口が遠くて行くのが大変な場合には便利です。
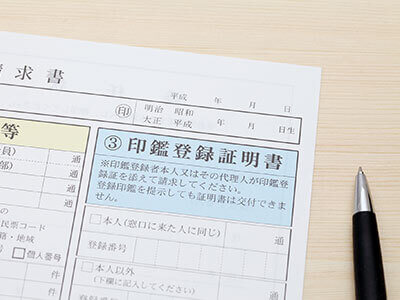
引っ越しをしたら印鑑登録はどうなるの?
手持ちの印鑑を実印として使うためには、住所地の自治体で印鑑登録する必要があります。それでは、引っ越しをした場合はどうなるのでしょうか。ここでは、引っ越しにともなう印鑑登録について説明します。
旧住所で自動的に登録が抹消される
別の市区町村へ引っ越しする際は転出届の提出が必要ですが、印鑑登録は転出届が受理された時点で自動的に抹消されます。印鑑登録については基本的に転出時の手続きは必要ありませんが、手持ちの印鑑登録証(カード)は返却、あるいは裁断します。自治体に確認したうえで指示に従いましょう。
印鑑登録が残ったままにならないか不安なら、引っ越しの前に印鑑登録を抹消することも可能です。手続きには以下のものが必要になります。
- 印鑑登録証
- 本人確認書類(免許証・保険証など)
- 登録している印鑑(必要の有無は市区町村により異なる)
同じ市区町村での引っ越しなら、転居届を提出することで印鑑登録の住所を新住所に上書きしてもらえるため、特別な手続きをしなくても印鑑登録を維持することができます。ただし、同じ市内への転居でも区が異なれば手続きが必要となる場合もあるので窓口やホームページ等で確認しておくと安心です。
新住所での新規登録が必要
前述のとおり、旧住所地での印鑑登録は自動的に抹消されますが新住所地の自治体で自動的に登録されるわけではありません。印鑑登録を希望する場合、新住所での新規登録が必要です。
転入届の提出時に行えば何度も窓口へ行かずに済みます。実印の規定の大筋は多くの自治体で共通していて、旧住所地の自治体で登録できた印鑑は新住所地の自治体でも実印として認められることがほとんどです。以前登録していた印鑑もそのまま登録できます。
新たな印鑑を登録するなら、転入先自治体の「印鑑条例」を確認しておくとよいでしょう。
引っ越し前に発行した印鑑証明書は使用できない
転出にともない印鑑登録が抹消されるため、引っ越し前に発行した印鑑証明書も無効になります。引っ越し先でなんらかの契約をする時、これまでの印鑑証明書は使えません。
もちろん、引っ越し前に印鑑証明書を添付して行った契約は有効です。引っ越し前に済ませる賃貸住宅契約については心配しなくてもよいでしょう。また、とくに指示のない限り新たな印鑑証明書を取得しての契約更新なども不要です。
印鑑登録の方法
引っ越し後に実印や印鑑証明書が必要になる機会はいつ訪れるかわかりません。いざという時に困らないよう、事前に登録しておくとよいでしょう。ここでは、別の市区町村へ引っ越した場合の印鑑登録方法について説明します。
印鑑登録に必要なもの
印鑑登録には以下のものが必要です。
- 登録を希望する印鑑
- 本人確認書類
運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどが代表的ですが、健康保険証など顔写真がない書類を複数組み合わせて本人確認に使用できることもあります。必要な身分証明書について、あらかじめ新住所地の自治体へ問い合わせておくと安心です。
代理人による申請の場合も登録を希望する印鑑は共通ですが、本人の申請時とは必要なものが少し異なります。
- 登録を希望する印鑑
- 代理人の本人確認書類
- 印鑑登録する人の本人確認書類のコピー
- 印鑑登録する人の自筆の委任状と回答書(もしくは代理人選任届)
また、手続きには印鑑登録申請書が必要ですが自治体窓口で直接記入するだけでなく、自治体WEBサイトでダウンロードして事前に用意したものを持参できるところもあります。
印鑑登録手数料は自治体によって異なるものの500円以下であることが多く、無料の自治体もあります。
身分証明の内容と本人による申請かどうかで登録までの流れは異なる
新住所地の自治体窓口で印鑑登録をする際には、記入済の印鑑登録申請書の提出から印鑑登録証(カード)発行までの流れを把握しておきましょう。
◎本人による申請
・顔写真付き身分証明書がある場合
官公庁が発行する顔写真付きの書類を提示することで、申請日当日にすべての手続きが完了します。
・顔写真付き身分証明書がない場合
自治体窓口で所定の手続きを行った後、自治体から「照会書」が届くのを待ちます。照会書に必要事項を記入したうえで再び窓口に出向くと、手続きが完了します。
手続きを即日完了させたければ保証人を立てる方法もあります。保証書欄に保証人が自筆で住所・氏名・登録番号を記入するほか、保証人の登録印鑑(実印)の押印が必要です。また、保証人が管轄自治体以外に住んでいる場合は保証人の印鑑証明書の添付も欠かせません。
◎代理人による申請
代理人が手続きする場合、申請後に登録者本人宛に照会書が送付されるため本人が照会書の「委任状」「回答書」の欄に記入し、代理人に渡します。代理人は照会書と登録する印鑑、代理人の本人確認書類を窓口に持参すると印鑑登録証が発行されます。照会回答書には提出期限が定められているため、くれぐれも忘れないようにしましょう。
なお、登録方法や手続きの詳細は「印鑑条例」により自治体ごとに定められていて、登録先によって異なる場合があります。新住所地の自治体Webサイトなどで必ず確認しておきましょう。
印鑑登録にまつわる疑問
ここまで印鑑登録の登録方法などを解説しましたが、最後に印鑑登録にまつわる疑問点について紹介します。
同じ市区町村内で引っ越した場合も印鑑登録は必要?
引っ越し先が同じ市区町村の場合、手続きは不要です。新住所への引っ越し後に転居届を提出すると印鑑登録申請時の住所も自動的に変更される仕組みです。また、これまで使用してきた印鑑登録証(カード)も継続して使用することができます。
一度登録した印鑑登録を廃止・抹消できる?
引っ越し後に新規登録した印鑑登録が不要になることもあるでしょう。そのような場合は、自治体窓口にて印鑑登録廃止手続きをすることができます。
登録者本人が印鑑登録廃止手続きをするときは、印鑑(認印可)、印鑑登録証(カード)、本人確認書類を持参します。代理人による手続きの場合は、登録者の登録印(実印)、印鑑登録証(カード)、代理人の印鑑(認印可)、抹消したい本人の直筆による印鑑登録委任状、代理人の本人確認書類の持参が求められます。必要なものは自治体によって異なる場合がありますので、Webサイトで確認したり直接問い合わせたりしておくと、当日の手続きがスムーズです。
印鑑登録できるはんこには決まりはあるの?
引っ越し前に登録していたものと同じ印鑑を使用する場合は問題ありませんが、新しく印鑑を登録する場合は規定に合う印鑑かどうかの確認が欠かせません。そのためにも、実印に必要とされる条件を知っておきましょう。
・登録可能な印鑑
印影が8ミリ角より大きく、25ミリ角より小さい印鑑が登録可能です。また、住民基本台帳に記載されている氏名(氏または名もしくは氏または名の各一部を組み合わせた場合も)を彫ったものなどが該当します。
・登録不可な印鑑
素材がゴムなど変形しやすいものや破損しやすいものは使えません。また、印影が不鮮明なもの、文字の判読不可のものなども登録不可となります。市販の三文判など、多くの場所で入手できる印鑑は悪用される恐れがあるため使わないほうが無難です。自治体の注意喚起に従いましょう。
印鑑登録の手続きに期限はある?
印鑑登録の手続きは義務ではなく、明確な期限もありません。
しかし、印鑑登録の手続きが完了していないと印鑑証明書を発行することができません。不動産取り引きや自動車登録などで印鑑証明書が必要になった時に焦ることのないよう、早めに済ませておきましょう。
後回しにするよりも移転元や移転先での各種届け出の提出時に一緒に手続きしてしまうとスムーズです。
引っ越しをしたら忘れずに印鑑登録の手続きを
引っ越し後に車を購入したり、住宅ローンを利用したりする予定がある人は転入手続き時に印鑑登録をしておくと便利です。何度も窓口へ行かなくても済むよう、引っ越し先で必要な手続きや持ち物については事前によく確認しましょう。
-
引っ越し業者へ無料で見積もり依頼




